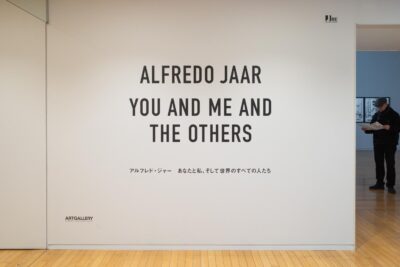2026.02.20
SMEGのショールームへ。
先日、イタリアの家電ブランドSMEG(スメッグ)のショールームへ伺いました。 キッチンの設備機器として、日本ではあまり耳馴染みのないメーカーかもしれませんが、 世界シェアを誇る創業1948年の老舗家電メーカーで、 ここ最近、本格的に日本に参入され、これから目にされる機会が増えていくメーカーだと思います。 まずはレンジオーブンとオーブンからご紹介します。 SMEG独自の機能で関心したのは、 ①オーブンにはエアフライ機能がついていて、揚げ物もできちゃいます! (エアフライヤーって案外場所をとりませんか?) ②ドア材はガラス3層構造になっているのですが、 なんと扉材が簡単に分解できて、洗えるんです! 使っているうちに、なぜだか扉のスキマに汚れが入りこんだりしませんか? SMEGだと扉が外せるのとで、そんな汚れもとても簡単にお掃除できます。 庫内のお掃除をするときはオーブンの真ん中に水を入れて、 蒸気で蒸すような感じで、汚れやこびりつきを取り除けて すっきり衛生的にお掃除できるなぁと感じました。 そしてレンジオーブン。 海外メーカーの場合、レンジオーブンは庫内の大きさが割と小さめで それゆえ、導入を断念される方もいらっしゃいますが SMEGでしたら、しっかりした庫内サイズのレンジオーブンがあります! 他社同様、コンパクトなサイズのレンジオーブンもありますが、 その場合はオーブンと並べて設置する場合に、ウォーマーをセットすることで 見た目もスッキリ、ラインを整えることもできます。 レンジフード、水栓、シンク、ワインクーラー、と魅力のある商品がまだまだありますので、 またご紹介させていただけたらと思います。 高橋 ___ Basisは、木工家具職人による細やかな手仕事を大切にしたオーダーキッチンメーカーです。 キッチン全体の雰囲気だけではなく、家具のように細かい部分までとことんこだわって作ることがとても得意です。 オーダーキッチンをご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。 Basisのキッチンづくりについて Basisの製作事例について Basisのショールームについて